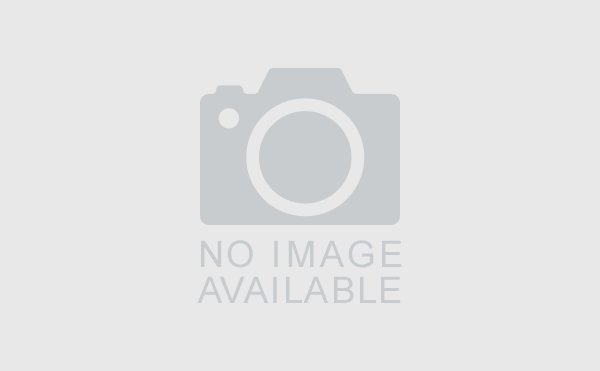第3回:「またITプロジェクトが頓挫…」その原因、実は「依頼側」にあった!?経営者が陥る失敗の罠

皆さん、こんにちは。株式会社リインフィット代表取締役の田邉です。
「新しいシステムを導入したのに、結局使いこなせていない…」
「多額の投資をしたのに、期待したほどの効果が出ていない…」
「気づけば予算は膨らみ、納期は遅れ、最後はプロジェクトが立ち消えに…」
社長の皆さん、ひょっとして、こんな苦い経験、ありませんか?
IT投資は、企業の成長にとって不可欠な要素です。しかし、残念ながらITプロジェクトの失敗は少なくありません。
経済産業省の調査(2020年)によると、DX推進中の企業のうち、約9割が何らかの課題に直面しており、その中でも「既存システムの老朽化・複雑化」や「人材不足」と並び、「費用対効果が不明確」といったプロジェクト推進上の課題が上位に挙げられています。
- 参考資料: DXレポート2中間取りまとめ(概要) (経済産業省)
ITプロジェクトがうまくいかないと、時間、予算、そして何よりも社員のモチベーションという貴重なリソースが無駄になり、企業の成長に大きなブレーキをかけてしまいます。
プロジェクト失敗の原因は多岐にわたりますが、今回は特に「依頼する側、つまり自社(経営者・担当部門)に潜む落とし穴」に焦点を当てて、その原因と対策についてお話しします。
ITプロジェクトの成功率は年々向上しているが…?
ITプロジェクトの成功率は、実は年々少しずつ向上しています。各社の提供している過去の調査結果を見ると、日本のITプロジェクトの成功率は以下のように推移していました。
- 2003年: 26.7%
- 2008年: 31.1%
- 2018年: 52.8%
- 参考資料:
一見すると、2018年には半数以上のプロジェクトが成功しているように見えます。
これは、プロジェクトマネジメント手法の普及や、専門知識を持つ人材の増加によるものと考えられます。
しかし、残念ながら最新の状況を見ても、ITプロジェクトの道のりは依然として険しいのが現状です。
情報処理推進機構(IPA)の2023年の調査では、システム開発プロジェクトの実に70%以上が、何らかの形で当初の計画通りに進んでいないという厳しい現実が指摘されています。
つまり、成功率は向上しつつあるとはいえ、裏を返せば約半数から7割ものプロジェクトが、いまだに何らかの課題を抱え、当初の計画通りに進んでいないのです。
この「成功しきれない」半数以上のプロジェクトに、実は依頼側である貴社の責任が大きく関わっているケースが少なくありません。
「まさかうちが?」ITプロジェクト失敗に繋がる依頼側の”あるある”落とし穴
「失敗の原因はベンダー側にあるはずだ!」
そうお考えになる経営者の方もいらっしゃるかもしれません。もちろん、ベンダー側の問題も存在します。しかし、多くのケースでプロジェクト失敗の根源は、実は依頼する側の「準備不足」や「認識不足」にある、というのが私の経験からの実感です。
1. 目的が不明確な「丸投げ」
「とりあえず、うちもDXしなきゃ」
「〇〇社のシステムが良さそうだから、うちも導入して」
といった漠然とした発注は、失敗の典型です。
- IT担当者:「社長の鶴の一声で急に話が進むけど、目的が曖昧で現場に落とし込めない」
IT担当者:「ベンダーに聞かれても、何がしたいのか明確に答えられない…」 - 「何のために」「何を達成したいのか」という目的が曖昧なまま、システム導入そのものがゴールになってしまいます。結果として、ベンダーも最適な提案ができず、完成したシステムが現場のニーズに合わない「使われないシステム」になりがちです。
- また、「いきなり大企業と同じような最新システムを入れる」といった、身の丈に合わない、流行に流された推進も危険です。
2. 要件定義の甘さと「言ったはず」のすれ違い
プロジェクトの成否を分ける最も重要なフェーズが「要件定義」です。ここで「これで大丈夫だろう」と甘く見積もってしまうと、後々の大きな手戻りやトラブルに繋がります。
- IT担当者:「後から『あれもこれも』と追加要望が出る!」
IT担当者:「最初にしっかり決めてくれないと、ベンダーにも説明できないし、開発が進まない…」 - ざっくりこんな感じで」と曖昧な指示で進めたり、依頼側とベンダー間でシステムの機能や仕様に関する認識のズレが生じたりします。
- ベンダーは超能力者ではありません。貴社の業務や課題、本当に実現したいことを全て読み取ることは不可能です。したがって、依頼する側が「自分たちの要望を正確に、具体的に伝える義務」を怠ると、開発が進んでから「こんなはずじゃなかった」と気づいても、修正には莫大なコストと時間がかかります。
3. 「任せきり」の姿勢と、適切なリソース・人員配置の欠如
ITプロジェクトは、外部のベンダーに依頼したとしても、自社の経営層や関係部門が主体的に関わらなければ成功しません。
- IT担当者:「社長がプロジェクトに無関心だと、他部署も協力してくれない」
IT担当者:「本業で手一杯なのに、プロジェクトの責任だけ重くのしかかる…」 - 「ITのことは専門家に任せればいい」と、プロジェクトの進行状況を把握せず、意思決定を遅らせたり、必要な情報提供を怠ったりします。また、プロジェクト推進のために、社内の適切な人材(情シス、各部門のキーパーソン)を確保し、十分な時間を割かせないことも問題です。
- 社長などの経営層こそが、システムを具体的にどうしていきたいか、どういう舵取りをすべきかを率先して決めて、従業員に明確に伝えていくことが必要不可欠です。わからないからといって報告だけをもらって何も関わらないのではなく、自らが「わかるようにする」という意識を持って率先してプロジェクトに深く関与することが求められます。
4. コストと納期への過度なプレッシャー
「安く早く」は経営者にとって当然の願いですが、ITプロジェクトにおいては、そのプレッシャーが裏目に出ることがあります。
- IT担当者:「この予算と納期じゃ、まともなものは作れない」
IT担当者:「品質を落とすか、残業するか。板挟みで本当に辛い」 - 非現実的な予算や納期をベンダーに押し付け、無理な開発を強いることで、品質の低下や、ベンダー側の不満、さらにはプロジェクトの途中で担当者が疲弊し、離脱するといった事態を招きます。
プロジェクト失敗の連鎖を断ち切るために、経営者ができること
ITプロジェクトの失敗は、会社の信用や未来を損ないかねません。
場合によっては、損害賠償を巡る訴訟に発展し、発注側が敗訴するといったケースも実際に発生しています。
例えば、過去の裁判事例では、発注側の要件が不明確であったり、仕様変更が頻繁に発生したりした結果、ベンダー側の開発が遅延・困難になったと認められ、発注者側の主張が退けられたケースがあります。これは、ベンダー側だけでなく、発注者側にもプロジェクト管理や要件定義における責任があることを明確に示したものです。
このような事態を避けるためにも、プロジェクト失敗の落とし穴を事前に認識し、適切に対処することで、成功確率は格段に高まります。
経営者の皆様に、ぜひ意識していただきたいのは以下の点です。
- 「IT投資の目的」を明確にし、全社で共有する
- 何のために、どんな効果を得たいのか、具体的なゴールを明確にしましょう。そして、世間の流行や大企業の事例にただ流されるのではなく、自社の課題解決や成長戦略に本当に資するIT投資であるかを見極めることが重要です。
- 要件定義には時間をかけ、関係者全員で取り組む
- 曖昧さをなくし、徹底的に議論することで、手戻りを最小限に抑えられます。
- プロジェクトにコミットし、適切なリソースを投入する
- 経営層が主体的に関わり、社内の適任者をプロジェクトに専念させる環境を整えましょう。
- 「適正なコストと納期」を理解し、ベンダーと対等なパートナーシップを築く
- 無理な要求はせず、プロの意見を尊重し、共にプロジェクトを成功させる意識が重要です。
- 社内のITリテラシー向上と人材育成にも投資する
- ITプロジェクトの推進には、ベンダーとの適切なコミュニケーションや、完成したシステムの運用を担う社内側の理解が不可欠です。全社員のITリテラシーを高める教育や、IT部門・担当者のスキルアップ支援に積極的に投資することで、プロジェクトの成功確率を飛躍的に高められます。
ITリソースが限られる中小企業のための具体策
「そうは言っても、うちには専任のIT担当者もいないし、プロジェクト推進のノウハウもない…」
そう思われる経営者の方もいらっしゃるかもしれません。ご安心ください。ITリソースが限られる中小企業でも、ITプロジェクトを成功に導くための道はあります。
- 「プロジェクトマネジメントを補完する外部の目」を入れる:
- 社内に専任のIT担当者がいなくても、ITプロジェクトの経験が豊富なコンサルタントやITパートナーを一時的に活用し、要件定義の支援やベンダーとの橋渡し役を担ってもらうことができます。
- 彼らは、貴社の状況を客観的に判断し、適切なアドバイスを提供してくれるでしょう。
- スモールスタートで「成功体験」を積み重ねる:
- いきなり大規模なシステム導入を目指すのではなく、まずは部署内や特定の業務に限定した小さなIT化から始めてみましょう。成功体験を積み重ねることで、社内のITリテラシーやプロジェクト推進のノウハウが蓄積され、次のステップへと繋がりやすくなります。**「小さく始めて、成功を広げていく」**という堅実なアプローチが、中小企業には特に有効です。
- IT導入補助金などの公的支援を活用する:
- 中小企業向けのIT導入やDX推進を支援する国の補助金制度も多数存在します。これらの制度を積極的に活用することで、費用負担を軽減し、より計画的にIT投資を進めることが可能です。
- 例えば、IT導入補助金などがその代表例です。常に最新の情報を確認し、活用を検討してみてください。
ITプロジェクトの失敗は、貴社だけが経験するものではありません。しかし、その失敗から学び、適切な対策を講じることで、必ず成功への道は開けます。ITリソースが限られているからこそ、外部の知見を賢く活用し、確実な一歩を踏み出すことが重要です。
このコラムが、皆様のITプロジェクトにおける「依頼側の責任」について見つめ直し、次なる成功への一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。
次回は、「ITプロジェクトがなぜ失敗するのか?」というテーマをさらに深掘りし、今度は「ベンダー側の責任」に焦点を当ててお話ししますので、どうぞお楽しみに。